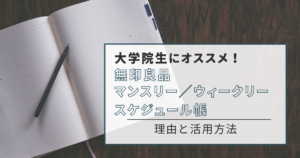大学のゼミで司会を担当するけど、進め方がわからない…。うまく進行できるか不安だし、みんなの前で話すのは緊張する!
大学や大学院のゼミで、司会をしなくてはいけない時ってありますよね。
私は、10〜30人が参加する大学院のゼミで、たびたび司会をしてディスカッションを進行しています。
最初は緊張して本当に嫌でしたが、少しずつコツを掴むことができました。
この記事では、ゼミや話し合いの場での司会進行のコツについて、まとめておきたいと思います。
司会者の役割


まず、司会者の役割について整理しておきましょう。
司会者とは、その言葉の通り「会の進行をつかさどる人」のことです。
主に、司会者には以下の役割があると考えます。
① 時間内に会が終わるように時間配分をする
② 参加者同士のディスカッションが活発に行われるようにサポートする
③ 必要時、タイミングを見計らって意見を取りまとめる
特に、①の時間配分をする役割は重要です。
発表の時も話し合いの時も、目安の時間を過ぎて続けてしまうと、参加している人は疲れを感じてしまいます。
どんなに面白い話でも、「あれ、時間過ぎてるけどいつ終わるんだろう…」と、だんだん集中力も低下してきてしまいます。
司会者の役割として、決められた時間内で発表者の発表と質疑応答を終わらせることが求められます。
実際にゼミを進行するためのステップ
では、実際にゼミの司会をする際に、私がどのように準備・進行をしているのかをご紹介します。
ステップ① 準備をする


まず、自分が担当するゼミの議題について、予習をしておきます。
参加者として参加する場合には予習をしなくても良いと思いますが、司会を担当する場合には必要だと思います。
予習の方法としては、事前に発表者や先生から送られてくる資料があれば、それに目を通しておきましょう。
ゼミの前にある程度内容が頭に入っていれば、質疑応答の際に発表者に確認や質問をすることが可能になります。
「いざ、質疑応答の時間になっても誰も発言しない!」といった時に、ディスカッションの皮切りとして司会者から疑問や感想を投げかけると、自然と話が盛り上がっていくことがあります。
ステップ② 議論の目的を確認して、ゼミを進めていく


いよいよゼミが始まったら、いつも他の人がやっているようにゼミを進めていきましょう。
例えば、こんな感じでしょうか。
「本日の司会を担当します○○です。本日は、△△さんの〜についての発表になります。△△さん、よろしくお願いします。」



簡単ですね!
発表者が発表し始めたら、Zoomであれば画面の共有ができているか、声の大きさは大丈夫かなどを確認し、必要であれば発表者に伝えてあげます。
ステップ③ 適宜質問をしたり、まとめたりして進行していく


発表者の発表が終わったら、質疑応答にうつります。
私はこんな感じでフロアの人に発言を促します。
「△△さん、ご発表ありがとうございました。(もし、誤字や確認が必要なことがあれば聞く。)では、質問のある方や感想がある方いらっしゃいましたら挙手をお願いします。」
もし、少し(30秒ほど)待っても手があがらなければ、司会者がディスカッションのきっかけを作ります。



日本人の文化的に、よほどのことがない限りすぐに質問が出ることは少ない気がします…。
司会者がはじめに質問をする場合は、簡単な確認や素朴な疑問で十分です。
なにも、超良い質問をする必要はありません!
ちょっと気になったことを聞いてみると、他の参加者も「これくらいのことを質問してもいいんだな」と思えるようになります。
例えば、私は言葉の意味や使い方、文章のつながりでよくわからなかったことなどを質問することが多いです。
また、時には途中で話をまとめることも必要ですね。
話がとぎれてしまったり、どんどん逸れていってしまうような時は、「ここまで〜〜というようなお話が出ていますが、この点についてご意見や確認したいことなどある方いらっしゃいますか?」などと言ってみると、ディスカッションを元の話に戻したり、後押ししてあげることができます。
まとめ:ゼミや話し合いでは積極的に司会をして慣れよう
以上、私なりにゼミや話し合いでの司会のコツをお話しました。
…とはいっても、私自身人前で話したり、手を挙げて意見を言うのは得意ではありません。
でも、もし話し合いをリードする役割ができるチャンスがあるのなら、積極的にやってみると良いと思います。
やってみると、自然と「どんなことを質問したらいいのか」「どれくらいの時間配分が丁度いいのか」が分かってきます。
初めは緊張するかもしれませんが、ぜひ頑張ってくださいね!