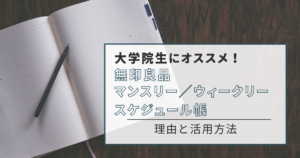お久しぶりです。看護系大学院生のぴーです。
時がすぎるのもあっという間で、博士課程の3年目になりました。
博士課程に進学してから、色々なことに悩んだり葛藤したりしていましたが、なんとかここまで順調に来られています。
今回は、「博士課程を乗り越える方法」をテーマに記事を書いてみたいと思います。
この記事では、以下のお悩みにお答えします。
- 博士課程の何が辛いのかを言語化したい
- 「つらい」という気持ちを少しでも楽にしたい
- 博士課程を乗り越える方法を知りたい
博士課程が「つらい」と言われる理由
よく、博士課程という言葉には、「つらい」「やめたい」「やばい」といったネガティブなワードが組み合わされていると思います。
私も、修士課程の2年間をスムーズに過ごしてきたので、博士課程も問題ないだろうと思っていました。でも、実際に博士課程に進学してみると、「つらいな」「今やめたらどんなに楽だろう」と思うことも多々ありました。
博士課程の辛さについては以前も記事を書いたことがあるのですが、簡単に理由を挙げてみます。
- 経済的に不安定な状態が長く続く
- 周囲の人とライフステージの差が生まれ、視線が気になる
- 自分で研究活動の全てを管理しなければならない

経済的に不安定な状態が続く

日本では当たり前ですが、博士課程でも学費の支払いが必要です。国公立でも年間50万円はかかってきます。
かといって仕事をたくさんできるほど暇ではない、むしろやるべきことだらけなので、不十分な収入のまま数年間を過ごすことになります。
お金は本当に大切で、お金に不安があると研究も思ったように進まないのが事実です。
周囲の人とライフステージの差が生まれ、視線が気になる

博士課程に進学すると、早くても27歳で博士号取得、修了となります。
私の場合は3年間の社会人経験を経てからの進学だったので、博士課程3年目の時点で29歳です。周囲の友人はどんどん結婚、出産といったライフイベントを迎えています。
幸い、私も2021年に結婚をして夫と生活をしていますが、出産は先延ばしにしていました。
最初は「自分のやりたいことを終えるまで家も買わないし、出産はしない!」と考えていました。でも、人の気持ちは変わるものだし、周囲の人の視線も気になってくるものです。
自分で研究活動の全てを管理しなければならない

修士課程とは異なり、研究は指導教授には基本的には頼らず、自分で進めていくことになります。
研究の計画から倫理審査、助成金の申請、学会発表、論文執筆、そのほか教育活動など…。
週1回3時間のゼミ時間以外は、全て自分でスケジューリングをして動いています。このスケジューリングによって、研究の進捗、収入、プライベートでの過ごし方、すべて変わります。これはかなりプレッシャー。
博士課程を乗り越える方法5選
経済的に不安定なまま数年間を注ぎ込む博士課程、私は「何をしているんだろう」「今やっていることに意味はあるんだろうか」なんて考えてしまうこともしばしば。
また、他の人と比較をして「自分は研究者に向いていないんじゃないか」と思うことも。
それでも、今まで続けられているのは、いくつかのことをしたからかなと思っています。
① 学会誌に論文を投稿する
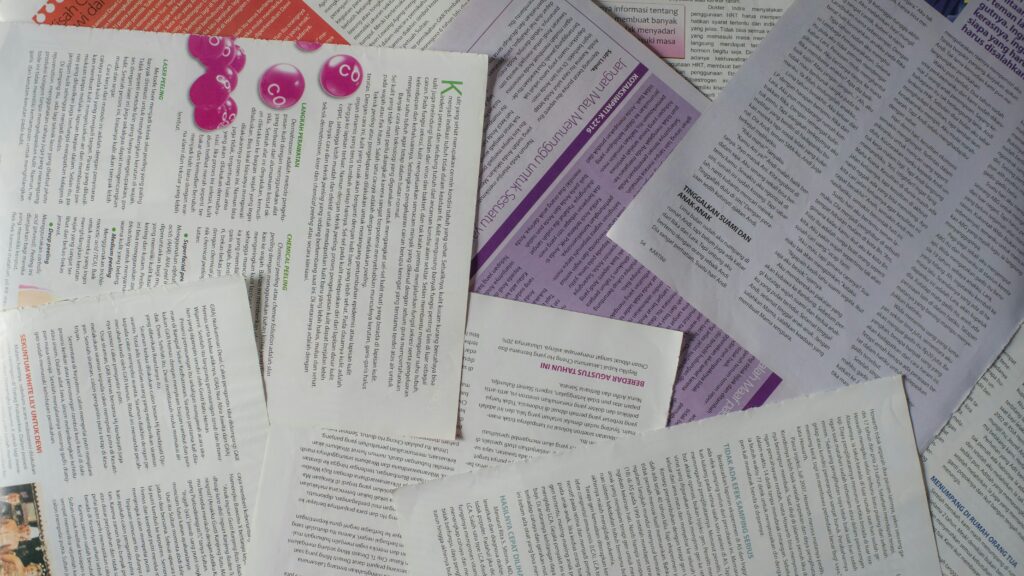
どこかで、「博士学生への最高のクスリは論文の採択だ」というツイートを見ました。まさにその通りで、学会誌へ論文を投稿し採択された経験は、だいぶ私のメンタルを維持させてくれています。
学位論文を書いたり、学会発表をするだけでは研究成果を広く発信したことにはなりません。日本語であれば全国へ、英語であれば世界へ信用のできる知見を発信できるのは、やっぱり論文の出版になります。
論文投稿には査読というステップがあり、最低2名の匿名の査読者の先生が自分が書いた論文を読んで批判的に指摘をしてくれます。
半年〜1年間かかる過程ですが、採択されれば今後一生業績としてリストに載せることができます。
博士課程で2本の査読論文が採択されて、今は「研究をして発信ができている」という実感と自信が持てています。
 ぴー
ぴー査読論文があると、「Researchmap」という日本の研究者情報データベースに登録することができます。論文以外の業績も整理できてとても便利です。
② 「こうじゃないといけない」を捨てる


博士課程といっても、いろんな研究室があり、さまざまな人がいます。
私は、「博士課程なんだからもっと研究に没頭しないといけないのかな」「1日に8時間以上研究している人もいる。自分は…」と他人と比較して落ち込んだことが多々あります。
でも、しばらくして、私は研究をしながら、家族との時間も大事にして、色々なことに挑戦する。100%研究にコミットして、全てを完璧にこなす必要はない。これが自分のスタイルだと気がつきました。
夫にも研究に没入できない悩みを打ち明けたことがあるのですが、「それ、花開かなかった時はこわいよ。マイペースに続けて色々挑戦している方がリスク分散になるんじゃない?」と言われました。
確かに、私はそういう人なのかもしれない、向いているのかもしれない、と納得しました。
③ お金を稼ぐ(支援金、助成金、バイトなど)


お金がないのであれば、その現状を変えるために「稼ぐ」ことを意識することが大事です。
「稼ぐ」といっても、バイト以外にも方法は色々あって、国や大学の支援金制度を活用したり、研究助成金を獲得したりすることで結構大きなお金を得ることができます。
学生の中でも、特に博士課程の支援は徐々に充実してきています。
私は2年連続で日本学術振興会の特別研究員DCには落ちてしまったのですが、大学の博士課程支援プロジェクト生として採択されて、毎月非課税の支援金をいただいています。
他にも、国や財団の助成金をいただいて留学や研究費に充てています。
バイトに関しては、看護師の資格を活用してクリニックと病院で働きつつ、業務委託で講師の仕事もしています。
業務委託の仕事に関しては開業して個人事業主として行っているので、経費計上で節税対策もする予定です。



博士課程3年目の現在は、新卒会社員程度の収入があり、だいぶ生活に余裕が出てきました。
④ 家族と支え合う


私は一緒に暮らしている夫がいるので、色々な面から支えてもらっています。
普通に考えたら、私がかなりの割合で支えてもらっているように思われがちですが、私も彼を支えることを意識しています。
例えば、土日は研究や仕事を休んで一緒に過ごしてリフレッシュできるようにするとか、「ありがとう」をいつも伝えるとか、彼の希望を聞いて折衷案を考えるとか、そういったことです。
側から見たら「奥さんがまだ学生をしていて、夫はその希望を実現するために支えていて大変そう」に見えると思います。でも、夫は「そうやってみられちゃうのは不本意。ぴーも色々考えて稼いでくれているし、家のことをしてくれている」と言ってくれています。
「支え合う」って意識しないと、自分よがりになってしまいがちです。修士課程の頃よりも、家族のありがたさを感じている今日この頃です。
⑤ 博士号を取得した後のことを妄想する


一般的に「博士号ってそんなにすごいことなの?」って感じだと思うのですが、アカデミックや研究関連のキャリアに進みたい場合は、大きなアドバンテージだと思います。
私は、学部を卒業して看護師を続けていたら病院でキャリアアップする道がメインでした。
でも、今は大学教員、政府機関、シンクタンク、将来的には国際機関といった選択肢が広がっています。
自分の好きなことで、ある程度自由度を持って仕事ができる日がとても楽しみです。そのためにはこれから数年は大変な日々ですが、それでも博士号を取得した後の進路を考えることは、大きなモチベーションになっています。
悩みながらでいい、一歩でも前に進もう
ここまで、博士課程のつらいところと、それを踏まえて乗り越える方法についてまとめてきました。
私は、今でも「今辞めたらどれだけ楽になるだろう」と考えることがあります。それでも続けられるのは、悩みを話せる家族がいて、辛くても前に進むと楽しみがあるからだと思っています。
頑張りすぎてメンタルを壊す人も多いので、自分も気をつけなきゃなと思っています。
今の自分を受け入れつつ、今日も一歩だけ進めればいい、そんな気持ちでこれからも博士課程を過ごしていきたいと思います。